『演劇書簡 -文字による長い対話-』 応答:犬飼勝哉

『演劇書簡 -文字による長い対話-』 犬飼勝哉の応答
保坂和志の小説『もうひとつの季節』のなかで、「僕」の息子である五歳児のクイちゃんが、「僕」の実家で見たまだ生まれたばかりの「僕」の白黒写真にこだわり、「あの赤ちゃんはパパが赤ちゃんだった時のパパなんだよね」と何度も確認する場面があります。いっぽう「僕」のほうは写真に写り込んだ大きな猫の存在に、なんとも形容しがたい感覚をおぼえています。
その感覚を「僕」は「世界がある」と表現します。もう中年である「僕」には身の回りにいる犬や猫などの動物たちが自分よりずっと年下なのが当たり前になっていて、そんな時に自分より先に生まれた猫の姿を見せられて虚を突かれた、とこの「世界がある」感覚を説明します。
この世界はもちろん自分が生まれる前から存在していて、おそらく何万年も前から猫はずっと居続けたわけなのだけれど、言葉では理解できたつもりでも本当の理解には及ばない、その認識の歪みみたいなものを「世界がある」と言い表しているわけです。
息子のクイちゃんも「僕」も、昔の白黒写真を見たことで「世界がある」現実にふいに触れました。人間の脳は個人のものでしかないから、思考というものは個人を端に発するしかなく、私たちは「世界」を自己の領域からしか捉えることができません。たとえば自分が存在しているのは父親と母親がいたからで、その父親と母親にもそれぞれ父親と母親がいて…、という繋がりは過去へとずっと遡っていくことができるわけですが、その過程のさまざまな偶然によって自分が存在することになったわけで、過去のどこかのタイミングがほんの少しズレただけで存在そのものがなかったという事実も、言葉では理解できたようなつもりでも、きちんと考えていくとまさに自分自身が宙吊りになるような、つまり「世界がある」ことに触れます。「世界」は自分とは関係なくそこに横たわっています。
2016年のマレビトの会『福島を上演する』で上演された「スターバックスコーヒーにて」の話をします。舞台はスターバックスの店内。老夫婦が上手の手前にいて、妻が夫にトイレを勧めます。おそらく脚の悪い夫のために妻はトイレが空いているかどうか確認しに席を立ちます。そして戻ってきた妻が「女ははいってたけど、男はあいてた」と告げると、夫はトイレに向かって歩き出します。しかし夫の足取りはとても遅く、さらにトイレは下手奥にあります。
その最中、一人の男がレジカウンターにやってきます。注文しコーヒーを受け取ると、彼は店内にいた男性客の座る真正面に向かい、腰かけます。やってきた彼は自分が天使だと打ち明け、先に座っていた男は天使に促されるように語りはじめます。
戯曲を書くために福島に取材にやってきたこと、一日じゅう街を歩き回ったけれども何もわからなかったこと、そして行き先のわからない電車に乗ったこと、天使は男にしか見えない存在で、天使に語る言葉は男の心の声です。
男の乗った電車は次第に街を離れていきます。ふいに降りた無人駅で、目的もなく真っ暗な道を歩いていると点滅する光に出会います。その光を見ていると動けなくなり、今もまだ自分はそこにいる、と男はスターバックスの店内で語っているのです。
そこにトイレを終えた老夫婦の夫が戻ってきます。相変わらず歩みは遅く、席に戻るまで時間がかかります。ようやく席に戻ると、待っていた妻とともに去っていき、店内には喧騒だけが残ります。
語る男は、この戯曲の作者自身を思わせる私的な存在です。彼の語りも極めて私的で、戯曲が書けないという苦悩、彷徨い歩き、そして世界の中心ともいえる発光に遭遇したこと。しかしそんな個人的で私的な語りは、昂りに達したところで、スターバックスに居あわせた老夫婦の時間の流れに対峙させられます。
ここで私たち観客は、戯曲を書かなければならない男の苦悩が、まるで一笑に付されたような気持ちにさせられます。誰によって一笑に付されたのかというと、それは現実に、であり、さらに「世界」に、とも言えます。街に、とか、生活に、とも言い換えることができるかもしれません。私たちはそれぞれが個人として個人的な事情を抱えるわけですが、それとは関係なく「世界」があるという事実。個人的で私的なものが「世界」に飲み込まれる時の、ある種の清々しさというか感動というか、この感覚はいったい何なのでしょうか。この戯曲の主人公ともいえる男は、最後には喧騒のなかに埋没してしまいます。
ところで演劇にかかわらず作家は、ある種の「叫び」を期待され要求されるところがあります。その作家が何を思い、どのような問題意識のもと、それはつくられたのか。作家がどういう立場から何に対し「叫んで」いるのか、そう問われる場面は少なくないし、また作品はそのような態度のもと読み解かれることが常です。そして「叫び」とは、個人から発される私的なものです。
しかし「世界がある」という現実に、私たちはどのようにアプローチできるのでしょうか。「世界がある」ことが気になってうまく「叫べ」ない、だからぼそぼそと喋る、ニヤつきながら言う、あるいは押し黙る。そのような態度しか取りようがないのかもしれません。
僕は昔、ちりめん山椒を30グラム測ってパッケージする作業をアルバイトでしていたことがあるのですが、作業をつづけていくうちにプラスチックのケースに盛ったちりめんの分量が感覚的にわかってきます。盛りの具合(視覚)と手に持った感覚(触覚)でだいたい30グラムが感じ取れるようになります。大鍋で炊いたちりめんをその日のうちに詰めていくので、その作業は一日がかりなのですが、作業の終盤にはかなりの精度で30グラムが判るようになります。
作品をつくることと「世界がある」ことを結びつけて考えると、僕はこのちりめん山椒のことを想起します。どういうことでしょうか。この結びつきを自分でもうまく説明できる気がしないのですが、あえて言葉にすると、実際にそれ(「世界」/ちりめん)に触れながら、触れている時間とともに、扱い方の精度が徐々にあがっていく、というものです。時間経過とともに身体感覚として落とし込まれていき、その経験によって身についた手癖のなかに「世界」を感じる、といったらいいのでしょうか。手癖も「叫び」と同じく個人から発されるものですが、声が大きいか小さいか、あるいはその声に自覚的か無自覚か、というところに違いがありそうです。そして手癖の伴わない「叫び」には、僕はあまり面白みを感じることができません。
手癖はあくまで手癖であって、メソッドのようにして集団内で強固に共有されるレベルのものではありません。メソッドとはその特殊性を顕示するという意味では一種の「叫び」みたいなものだから。
ところでひとつだけお聞きしたいのですが、松田さんの言う「母を嫁がせる願望」というのは、ここまでで述べてきた「世界がある」という感覚に、どこか似たところはありますか。
*
演じられた劇のようにも見え、同時に現実世界の事物のようにも見える「態の演劇」では、それが置かれる空間的な広さの違いで見え方が大分違ってくるように思えます。またそれを近くで見るか遠くから見るかでも違いそうです。
そもそも「態の演劇」では「置く」という表現がとてもよく似合います。それをどこに置くのか。『福島を上演する』の2016年と2017年の上演では、舞台空間の広さに極端な違いがありました。体育館が会場となった2016年に対して、2017年では客席のキャパがおそらく100人にも満たない劇場空間での上演でした。
具象的な舞台セットを持たない「態の演劇」では、演技者の演技によって現実とは「異質な時空間」がそこに発生します。演技者を中心に、それは同心円状とは言わないまでも、周囲の空間に広がっていきます。空間は劇場そのもの、あるいは体育館そのものの顔をもちつつも、同時に劇空間になります。観客は演技者の動作を見ながら、同時に演技によって周囲に広げられた風景を虚空に見ることになります。
広い空間でそれが為された場合、風景が広がる余白が十分にあるため、描かれた街を幻視します。この時、演技者の個人としての存在は希薄になります。さらに舞台から客席までの距離が離れている場合、演技者の顔は物理的に視認しにくくなるため、そういった意味でも「個」は薄められます。つまりカメラをズームアウトするかのごとく、人物を含んだ風景そのものが浮かび上がることになります。
ここで「態の演劇」が狭くて近い場所でおこなわれたとします。すると、今までは空間を見ていた観客の視線は演技者の動作そのものに向かいます。そして距離が近い分、演技者のもつ固有の顔がはっきりと見えます。ここで観客は「態の演技」について思考することになります。いったいどのようなメカニズムのもと「態の演劇」がおこなわれていたのか。いわば解明するような視線をそこに投げかけます。
余白を剥奪されたことで、「世界」のなかにいるそれぞれの「個」にカメラはズームアップしてきました。観客は空間ではなく動作を見ようとします。「世界」のなかにいる「個」とはどのようなものなのか、そのふるまい方に今や視線は向かっています。2017年の上演(キャパ100にも満たない劇場)では2016年の上演(体育館)と比べて、演劇とは何か、演技とは何か、という問いが上演に際して多く生まれたのが印象的でした。また上演された戯曲にもそのような問いかけをする仕掛けのものが複数あるように感じられました。
ところで「態の演技」とはどのようなものなのでしょうか。演技者は「態の演劇」において、どのような演技をすべきなのでしょうか。
「態の演劇」が単なる「演劇の態」にならずにかろうじて演劇であることを保つには、なにかコツのようなものが要りそうです。それはまさに手癖のような微細な匙加減によってそうなっている、としか言いようがないのかもしれませんが、ひとつだけ要因としてここで挙げたいのが「断片的なリアリティ」の有無というものです。
わかりやすい例として、たとえば固有名詞。施設名称だったり、町名や駅名だったり、河川の名前、あるいは「道の駅」で供される定食の名称。それらがもつ響きの独特なリアリティ(実際に福島という都市のなかにあり、個人が想像で考え出した名ではないという意味で、これも「世界」です)が断片的に散りばめられることで、それが全体の重石となり、「態の演劇」をその場に留まらせている、とでも言えるでしょうか。これに関して言えば、劇作者が実際に現地を取材をしているという事実が、さらにその強度を上げているところもありそうです。
演技者がおこなう「態の演技」においても、たとえば松田さんが例にあげたような、ものを食べる動作の時に「味が来る」のを想定したり、手に持ったコップの冷たさを感じたりすることは、まさしく断片的なリアリティだと言えるのではないでしょうか。そしてそのような一点集中的な細部描写が重石となって、テーブルからコップを手に取る動作や指のかたちの疎かさの許容が可能となります。この一点集中的なディテールの深化は、演技者の内面にのみ影響を及ぼすというより、きっと普通に目に見えるかたちで効果がありそうです。腕の振りのアタックポイントがズレるようなかたちで、おそらく動き方に変化を及ぼします。
ともすると「態の演技」は、ただうわべだけをなぞって良しとしてしまうような「演技の態」、つまり単なるフリのようなものになる恐れがありますが、それが「態の演技」か「演技の態」かは、この断片的なリアリティの有無に寄っているのではないかと想像します。そして断片的なリアリティは、演技者の「個」からしか発生しようのないものだと僕には思えます。
「個」を希薄化し「世界」を描く欲求に応えられる可能性をもつ「態の演劇」ですが、それを担う「態の演技」はどうしても「個」を発端としなければならない、と言うと矛盾しているようですが、僕にはこの点において、どうしても見る側と演じる側のあいだに断絶が存在するように感じられるのです。
「態の演劇」を見る側の演出者と「態の演技」をおこなう側の演技者が、この断絶を意識せずにいち集団として意識を共有しようとすると、たとえば演出者が「態の演劇」を演技者に対し意識づけすぎたりすることで、演技者の「態の演技」を「演技の態」へと近づけてしまうようなことが起こりそうです。そして「演技の態」をすることはそれほど難しくないだろうし、おそらく安定した状態なので、簡単にそこに陥ってしまう危険性があるように思えます。
いただいた書簡のなかで、演技者の表現が「既存の個人的な経験へと承認されることにとどまる」ことは「不十分」ではないか(『演劇書簡 -文字による長い対話-』1)、と疑問を持たれていますが、おそらく松田さんが想定されている、(僕の言葉で言うところの)「個」が希薄となった、いわば無機的なふるまいをする演技者は、演技者として何を起点としてふるまうのが適切でしょうか。またそのようなふるまいは実際のところ、どの程度可能なものなのでしょうか。いずれも演技者目線からの疑問と言えるかもしれません。
往復書簡ということなので、最後に質問をさせていただきました。ではこんなところで僕からの返答を終えたいと思います。お返事、気長にお待ちしています。
カバー写真:「木星からの物体X」撮影者:タカラマハヤ
(文・犬飼勝哉)
犬飼勝哉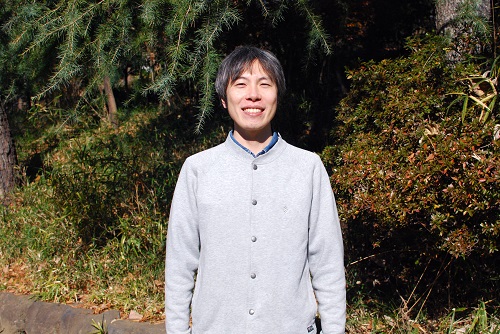
劇作家・演出家 1984年愛知県生まれ。京都にて舞台俳優として活動後、東京に拠点を移した2010年頃より自作をコンスタントに上演。現在は個人名義「犬飼勝哉」として活動する。 おもな作品に『必要と十分』(2013)、『スポット』(2014)、『木星の運行』(2015)、『木星のおおよその大きさ』(2018) など。 戯曲『木星のおおよその大きさ』が第18回AAF戯曲賞一次通過中(10月18日現在)。
マレビトの会『福島を上演する』 作・演出:マレビトの会

| 公演名 | マレビトの会 『福島を上演する』 |
|---|---|
| 日程 | 10/25(Thu)19:30・ 10/26(Fri)19:30・ 10/27(Sat)18:00★・ 10/28(Sun)14:00★ |
| 会場 | 東京芸術劇場 シアターイースト |
国際舞台芸術祭フェスティバル/トーキョー18
| 名称 | フェスティバル/トーキョー18 Festival/Tokyo 2018 |
|---|---|
| 会期 | 平成30年(2018年)10月13日(土)~11月18日(日)37日間 |
| 会場 | 東京芸術劇場、あうるすぽっと、南池袋公園ほか |