舞台美術家は、小さな「変異」を起こして街を変えていく ――セノ派・坂本遼インタビュー

昨年F/Tのオープニングプログラムを担当した舞台美術家コレクティブ「セノ派」が、今年は趣向を変えて新たな企画を発表する。
セノ派の一員、坂本遼は昨年と同じく南長崎エリアを拠点としながら、今年は映像によって日常と作品と鑑賞者の関係をデザインしなおそうとしているという。坂本はいかに舞台美術を通じて都市へアプローチするのだろうか? 坂本と舞台美術のかかわりを振り返りながら、今作にかける思いを尋ねた。

話しながらつくっていく
――まずは坂本さんと舞台美術のかかわりについて伺えたらと思います。何がきっかけで舞台美術の道に進むことになったのでしょうか?
大学で演劇や舞台美術を学んでいたわけではなかったんですけど、演劇を観るのが好きだったし木工家具もつくるデザイン事務所でバイトをしていたのでつくること自体も好きで。ふたつを足したら舞台美術かな、と。当時知り合いが通っていた大学で杉山(至)さんが授業をもっていたので潜り込ませてもらって、舞台美術に興味があるんですと杉山さんに伝えました。
――大胆ですね。大学では何を学ばれていたんですか?
哲学科の美学コースにいましたね。当時杉山さんに大学では哲学と美学を勉強していると伝えたら「じゃあ舞台美術だよ」と言われたことを覚えています(笑)。最初は一年続くかどうかもわからないくらいの気持ちだったんですが、結果的に続いてますね。
――杉山さんに出会われて、本格的に舞台美術の道に進んだわけですね。
2008年に大学を卒業してから六尺堂に通うようになりました。六尺堂はフリーランスの舞台美術家たちが集まるところなので、杉山さんの現場を見させていただいたり、ほかの方の現場に呼ばれていったり。当時は「上手と下手」など基本的な舞台用語もわからなかったので大変でした。いろいろな人を手伝っていくなかで、少しずつ自分の現場も増えていきましたね。
――現場を通じて舞台美術についても学んでいった、と。
いわゆる「基礎」を教えてもらうというより、いろいろな人のつくり方を学んでいきました。舞台美術家は一人ひとりつくり方が違うので、スタンダードがあるわけではなくて。でもいまだにわからないことはたくさんありますし、自分のつくり方みたいなものはまだ確立されていないと思います。それに、最初は自分と近い世代の人たちと一緒につくっていく現場が多かったので、美術はこうつくるものというより何をつくるのか一緒に話し合うところから始まっていた気がします。
――印象に残っている経験はありますか?
いまでも忘れられない失敗は本当にたくさんあります。赤字になってしまったこともあれば、3本同時に行われる公演すべての美術を担当してものすごく大変だったこともあり……。ただ、一番印象に残っているのは2017年にルワンダで「Ubumuntu Arts Festival」という芸術祭にセットデザイナーとして参加したことと、その翌年にゴリラネーミングセレモニーというルワンダの国民的行事のセットデザインを担当したことですね。

アフリカでの経験が教えてくれたこと
――ルワンダで舞台美術をつくるなんてかなり貴重な体験ですよね。
2015年に始まったUbumuntu Arts Festivalは首都キガリのジェノサイド・メモリアル・センターにつくられた野外劇場を舞台にした芸術祭で、ホープ・アゼダというディレクターが世界中からアーティストを招聘しています。2年続けたタイミングでアジア系のアーティストがひとりもいないのはおかしいということで、大使館を通じてアジア諸国に声がかかったらしく、巡り巡って六尺堂に声がかかったんです。日本でよく知られているフェスティバルではありませんでしたし、何が起こるかわからないから引き受けてくれる人がいなかったのかもしれません(笑)。六尺堂なら誰かいるだろうということで、ぼくと福島(奈央花)さんが行くことになりました。それまで担当されていた方が現地に来られなくなったそうで、2年目はゴリラネーミングセレモニーというゴリラの赤ちゃんに名前をつける式典の会場デザインも担当させてもらえることになったんです。
――演劇の位置づけも日本とは大きく異なっていそうです。
ルワンダにはあまり劇場がないので演劇を観る文化もないですし、単純に「知らない」ものですよね。フェスティバルでは演劇のワークショップも行われていましたが、やはり演劇のことを知っている人は少ない気がします。ただ、みんな歌や踊りは好きなのでパフォーミングアーツとの親和性は高いですし、野外で作業していると通りすがりの人から「どこで何を勉強すればこういう仕事に就けるのか」と聞かれることは多かったです。
――実際の制作はどのように進められていったんですか?
まずは事前にリモートでデザインに関する打合せを重ねたうえで、現地に一カ月ほど滞在して舞台づくりを進めていきました。ぼくと福島さんと現地の方5人ほどでチームを組み、図面や模型を見せながら説明して。資材市場をまわって板や鉄を買うこともあれば、竹を伐採しに行ったこともありました。もちろん日本とは文化も環境も違いますが、自分の手を動かしてつくるぼくらのスタイルはルワンダでもめちゃくちゃ通用しました。それまで舞台美術を担当していたデザイナーのマット・ディーリーさんは数々のプロジェクトを手掛けていることもあって現場に付きっきりで制作できるわけではなかったので、現地の人々にとっても最初から最後まで一緒につくっていくことは新鮮だったみたいで。もっとも、現場では毎日ケンカしてましたけどね(笑)。

“ハブ(hub)”としての舞台美術
――いろいろな経験を経て、いまはどのように舞台美術へとアプローチされているんでしょうか。
舞台美術は“ハブ(hub)”になれる存在だと思うので、つねにいろいろな人の話を聞くようにしています。もちろん自己表現も重要ではありますが、お客さんと作品や演出家と作品をハブとしてつないでいきたい。アフリカに行った際も、バックグラウンドも言語も宗教も違う人たちをつないでいける舞台の力を感じたんです。とりあえず目の前の舞台を観ようと思わせられる空間の強さはすごいなと。
――実際の制作ではまわりの人々とどうコミュニケーションをとっていかれるんですか?
いろいろなパターンがありますよね。確固とした戯曲があればその核をぶらさないよう演出家と話していきますが、20代の作家が新作を書くときなんて小屋入りまでに書き終えられることのほうが珍しいですから(笑)。演出家にイメージがあればそれを舞台にインストールするし、イメージはないけどパッションがあるならそれを生かしていく。何も決まっていないときは、演出家と雑談しながら考えていくこともあります。つくり方という意味では、お客さんのことを考えることはあっても、こういうお客さんが来るからその人に合わせようとすることはないかもしれません。
――つくるものは舞台美術ですが、コミュニケーションに重心があるわけですね。
実際に、いわゆる「舞台」だけではない領域でコミュニケーションを考える機会も増えてきていて。企業のイベントでアートコミュニケーションを考えるために何かしたいとか、0~3歳児向けのオペラをつくりたいとか、シェフがパフォーマンス形式で料理を振る舞いたいとか。企画だけ進んで実現しないものも多いんですが……。依頼としては「舞台美術」の制作を相談されるんですが、結局はお客さんにどう作品へ触れさせるか考えていく作業になりますし、舞台セットの話だけ考えていては対応できない。いまは誰もが大きな劇場で公演を打つことを目指す時代ではないですし、演劇や舞台芸術のバリエーションが豊かになっている気がしますね。いろいろな人と一緒に話したり考えたりできるのはすごく面白いです。

F/T19 『移動祝祭商店街』(写真:合同会社アロポジデ)
舞台ではなくまちの風景をデザインする
――昨年からF/Tで披露している「移動祝祭商店街」は実際の商店街で制作を行なうため、まさに多くの人とのコミュニケーションが求められそうです。昨年の制作はいかがでしたか?
正直に言えば、めちゃくちゃ大変でした(笑)。商店街に住む方々はF/Tはおろか演劇も舞台美術も知らないわけで、まったくつながりがないところから対話を始めていかなければいけない。だからこそ、劇場の中で行なっていたことを街の中で大きく展開させることではなく、その場所に自分が行って“ウイルス”のように変異を起こすこと、変異によって何かと何かをつなげていくことが重要なんだなと思いました。ささいな変異ですが、制作のために間借りしていたお店のおばあさんが最後に「じつはわたしずっと絵が描きたかったのよね。描きはじめてみようかしら」と言ってくれたのは嬉しかったです。
――今年はコロナ禍によってさらにコミュニケーションのかたちが変わりそうですが、どんな作品をつくられているんでしょうか。
こんな状況だからこそ、舞台上のセットだけではなくて、作品と鑑賞者のつなげ方をデザインしたいと思っています。外に出られず家にこもっていたときのひとりの世界と客席や舞台をつないでいくことで、今回杉山さんが提示したサブテーマでもある「一人でいられる方法」をデザインできたらなと。具体的には、落合南長崎のショッピングモールに“つくられた屋上”で映像を撮ろうと思っています。その屋上は当初は足湯などを設置して人がくつろげる空間になるはずだったのですが、結果的にいまは封鎖されていて誰も入れないんです。もはやそんな空間があることを知らない人もたくさんいて、歴史や文化、街とも途切れてしまった孤独な空間なんですよね。孤独な空間でつくるからこそ、去年のように何か街に変異を起こせると思っています。
――忘れられた屋上で、日常と風景のデザインを試みる、と。
屋上に舞台と客席をつくるつもりです。舞台の上にはセットがあり、客席から観客が作品を観ている。その様子を映像にします。キーになるのは窓ですね。観客は美術の窓を“ハブ”にして作品風景を見ているのですが、ウェブ上で映像を観る人=「観客」もブラウザという“窓”を通して観るわけですよね。窓の存在によって部屋の空気が変わったりその時々の景色が見えたりするように、この作品に触れたときに、まちや、観ているその人の日常にも、カーテンの隙間から光が漏れてきたり、窓から風がやさしく入ってきたりするイメージをもってもらえたら。そういう想像と景色をつなげられたらと思っています。いつもの風景を少し違った角度から眺めてみることが移動祝祭商店街がやろうとしていることだし、F/Tが届けようとしているものでもあると思いますから。

坂本 遼(さかもと・りょう)

1984年神奈川県生まれ。國學院大學文学部哲学科美学専修卒業。2009年から舞台美術研究工房・六尺堂にて舞台美術をはじめる。東京の小劇場を中心とした演劇の舞台美術をデザインから製作まで行い、映画美術やインテリアも手がける。2017年より東アフリカのルワンダ共和国にて行われるUbumuntu ArtsFestivalにセットデザイナーとして参加。2018年にはゴリラネーミングセレモニー(Kwita Izina)の会場デザインにも関わる。
もてスリム
1989年、東京生まれ。おとめ座。編集者。 トーチwebでシリーズエッセイ『ホームフル・ドリフティング』連載中。
舞台美術家集団が見出す “景”がまちと人にあらたな縁を結ぶ
『移動祝祭商店街 まぼろし編』

| 企画デザイン | セノ派 |
|---|---|
| 日程 | 10/16 (Fri) - 11/15 (Sun) |
| 会場 | 特設ウェブサイト、豊島区内商店街、F/T remote(オンライン配信) |
| 詳細はこちら |
忘れ去られた屋上が「街」と「観客」をつなぎなおす
『移動祝祭商店街 まぼろし編』Roofing the Roof with a Roof
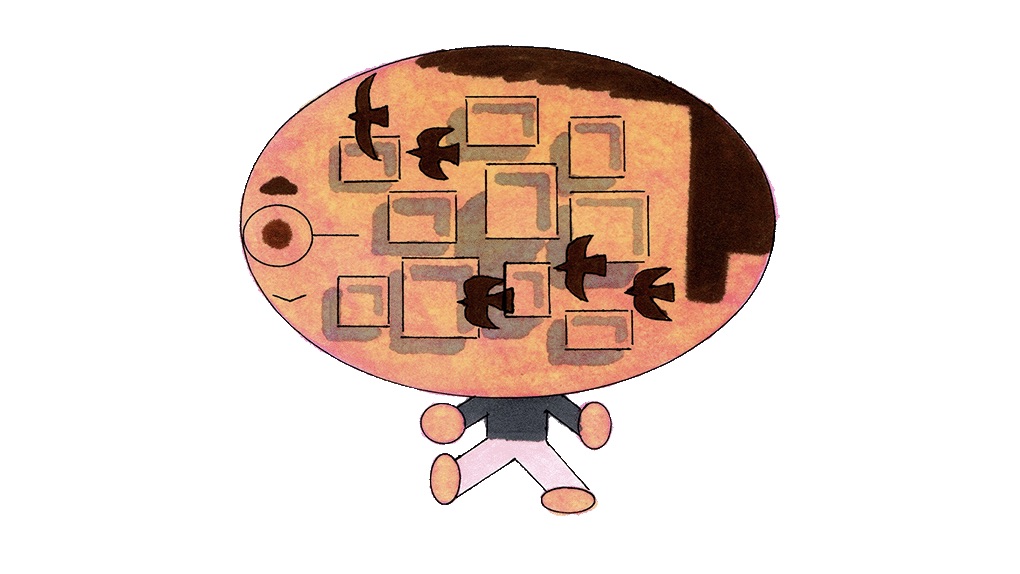
| 企画デザイン | セノ派 坂本 遼 |
|---|---|
| 日程 | 10/16 (Fri) - 11/15 (Sun) |
| 会場 | 特設ウェブサイト |
| 詳細はこちら |
人と都市から始まる舞台芸術祭 フェスティバル/トーキョー20
| 名称 | フェスティバル/トーキョー20 Festival/Tokyo 2020 |
|---|---|
| 会期 | 令和2年(2020年)10月16日(Fri)~11月15日(Sun)31日間 |
| 会場 | 東京芸術劇場、あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)、トランパル大塚、豊島区内商店街、オンライン会場 ほか ※内容は変更になる可能性がございます。 |
概要
フェスティバル/トーキョー(F/T)は、同時代の舞台芸術の魅力を多角的に紹介し、新たな可能性を追究する芸術祭です。
2009年の開始以来、国内外の先鋭的なアーティストによる演劇、ダンス、音楽、美術、映像等のプログラムを東京・池袋エリアを拠点に実施し、337作品、2349公演を上演、72万人を超える観客・参加者が集いました。
「人と都市から始まる舞台芸術祭」として、都市型フェスティバルの可能性とモデルを更新するべく、新たな挑戦を続けています。
本年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、オンライン含め物理的距離の確保に配慮した形で開催いたします。