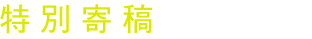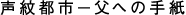- ホーム /
- プログラム /
- 声紋都市 ー父への手紙 /
- 特別寄稿
『声紋都市―父への手紙』 作品解説
「絶対的な周縁性」と「演劇」
森山直人(演劇批評家、京都造形芸術大学准教授)
『声紋都市―父への手紙』は、「マレビトの会」を結成してから6本目となる松田正隆の新作戯曲の上演である。
「マレビトの会」以降、松田正隆は変わった―多くの人は、そう口にする。実際のところ、何処でもない場所、登場人物の解体、うわごとのように発せられる台詞、といった、いかにも「前衛演劇的」な諸要素は、90年代に発表された純度の高い会話劇とは、ことごとく対極にあるように思われても仕方がない。けれども、だからといって、近年の松田が目指しているものが、たんなる伝統的な前衛演劇のスタイルのいまさらな模倣だというわけではない。それどころか、もしも、「絶対的な周縁性」とでもいうべきものに向けられるまなざしのあり方、という点からとらえ直してみるならば、「マレビト以前」から「マレビト以後」に至るまでの彼の作品世界は、むしろ首尾一貫しているように思われてくるのである。
絶対的な周縁性。いま、私はこの言葉を、きわめて曖昧な生の形態を呼び表すために使っている。それ自身が曖昧であるというより、曖昧さを強いられているような生。何かに完全に所属することもできなければ、完全に所属しないこともできないでいること。どちらか一方であれば、話は至極簡単である(「体制」と「反体制」、「日本人」と「外国人」、「生者」と「死者」・・・)。けれどもこの世界には、そうやってどちらか一方に分けることが絶対にできないものが確実に存在することもまたたしかだろう。1990年代後半以降の松田にとって、その最たるものは、カクレキリシタンが何百年にもわたって口伝で受け継いできたという祈祷の文句「オラショ」である。もともとラテン語のoratio(祈り)を語源としているカクレキリシタン特有の文化である「オラショ」は、カトリックのラテン語の祈祷文が、口伝で受け継がれているうちに元の意味がしだいに見失われていき、もはやラテン語とも日本語ともつかない音の連なりとして、いまでも長老たちによって暗唱されているれっきとした〈ことば〉である。「マレビト以後」の『島式振動器官』、『王女A』、『パライゾノート』、『アウトダフェ』などの作品では、しばしば実際の「オラショ」の一節が、唐突に会話を中断して発せられたりする。「西洋の言葉が僕の故郷の島に来て変容して土着化し、それをずっと喋っている人がいた。このことは、日本人を単一の言語を語る民族と思わないですむ一つの証しのような気はしています」(『舞台芸術』11号、松田正隆インタヴューより)。ここで彼自身が語っているように、演劇を生業とするようになってからの「オラショ」との出会い直しは、そのまま「母語」「母国語」とは何か、とりわけ、「日本語」という「母語」「母国語」を使って劇をつくることで、人は何を得て何を失うことになるのか、という根源的な問いかけを生じさせないわけにはいかなかった。「私たちが、母語として日本語をすらすら話せてしまうことが少しも自然ではなく、奇跡的なことのようにも思えるし、同時にまた悲しいことのようにも思える」――こうした趣旨の発言を、松田はいろいろな場所で行っている。そして、日本語をすらすら話せてしまうことの悲しさは、実はすでに彼が「マレビト以前」から描いていたものだったともいえる。
「マレビト以前」の松田の初期のリアリズム的な作品は、どれも一見抒情的で、美しい方言(長崎弁)で書かれているように見える。代表作の『海と日傘』では、不治の病をわずらっている女主人公が、小説家の夫と二人暮らしの家庭を、死の直前まで懸命に支えて生きようとする姿が印象的に描かれている。彼女は死の直前まで主婦としてのプライドを崩すことはなく、自分の死後の夫の再婚相手の心配までするほど、そのプライドは徹底している。だが、余命わずかとなったある日、夫の不倫相手らしい女性編集者の来訪を受けたとき、彼女が守り続けていた何かがついに決壊する。彼女はテーブルの上でこぼれたお茶を拭こうともせず、黙って夫の手を握りつづける。来客が去って再び二人きりになった家で、縁側の向こうの夕暮れのひだまりにたたずみながら、彼女は「うちのこと、忘れたらいけんとよ」と口にする。それがこの作品のなかで、女主人公が発する最後の言葉となるのだが、そこになお健気な女性の悲劇を読むか、あるいは底知れない悪意を読むかは、もちろん観客の自由に委ねられている。だが、ある意味でそれ以上に重要なのは、彼女が生前に、この言葉しか残すことができなかったという事実である(「マレビトの会」の松田正隆を知っている私たちにとっては、そのことのほうがよりクローズアップされて見えてくるのだ)。本当は夫にもっと激しい言葉で恨みをぶつけることも愛を要求することもできたかもしれなかったのに、彼女はそうできなかった(のかもしれない)ということ。夫は、死んだ妻が、本当は何を言いたかったのかを知る機会を永遠に奪われているが、それを奪った当のものは、ひょっとすると彼女の身に染みついた「母語」それ自体だったのではなかったかということ。たとえば彼女がラテン系の言葉を話す共同体に生まれていたら、こんなふうに寡黙でいることが逆に難しかったかもしれない、ということ。
「今もこうやって日本語喋れてますけど、なんで舌が日本語になっているのかとか、生まれて物心ついたら喋ってて、そういうことの奇妙さ、奇跡みたいなことはもう少し考えてみたいなっていうのがあったんです。そのことで演劇を続けるっていうことは、母語みたいにくっ付いて離れない、刻印されて刺青のように取れない声ですね。それを演出家として考えることと、俳優が台詞を覚えて喋るということがなんとなく繋がるんじゃないか」(マレビトの会HP、内野儀氏との対談より)。かりに、「美しい日本語」などというものが存在するとしたなら、まさにその言葉の「美しさ」に塗り込められたまま、永久に他人に伝達されることなく失われてしまった無数の「声」が、いったい歴史上どれほど存在していただろうかと想像してみること。そのような想像力こそが、「マレビト以前」と「マレビト以後」を緩やかに結びつける、松田の「絶対的な周縁性」へのまなざしである。そして「マレビトの会」とは、自らが日本語という母語でしか演劇ができない条件におかれていることを深いところで自覚しながら、それでも日本語を自明の前提とせずにそうするためには、どのような方法が可能なのかを模索するための機動性に富んだ集団なのである。
「父」の「声」へ向かって
この文章を書いている時点で、まだできあがっていない新作のことを無闇に想像するのは慎まなければならないが、それでも、おそらくはこの『声紋都市――父への手紙』でもまた、母語の存在によってはじめて伝達可能となった無数の「声」と、まさしく母語のせいで伝達されずに消えてしまった「声」とが、何らかの形で、ともども主題となっていくだろう。06年の『アウトダフェ』は、アウシュヴィッツで、ナガサキで、チェルノブイリで焼かれ、灰となった人々の声が堆積する巨大な廃墟を発掘する人々の物語であり、07年の『クリプトグラフ』は、イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』(72年)における「架空都市からの報告」というスタイルに倣い、「血液都市」「車窓都市」「分娩都市」といった、奇怪な名前の都市から送られてきた報告書(それらはすべて私たちが日常的に受け取っている無意味なスパムメールの「引用」で成り立っており、いわば暗号化され、意味を喪失した無数の声の集積物である)を、俳優たちが同時多発的に読みあげていく、という作品だった。「声紋都市」というフレーズは、『クリプトグラフ』に、架空の都市の名の一つとしてすでに登場している。声紋(Voiceprint)とは、いうまでもなく、個人の識別が可能な声の周波数分析を複雑な縞模様にグラフ化したものである。指紋がそうであるように、声紋もまた特定の誰かの痕跡にほかならないが、たんなる痕跡以上に、それは視覚的に変換された声の持ち主その人であるという印象を強く与えることになる。松田は、演劇と写真の類縁性に関心をもっているというが、その意味で、声紋とは、いわば「声を写した写真」であり、そうであるがゆえに、写真のように次々に複製され、まるで暗殺されたハムレットの父親のように、私たちの周囲を執拗に徘徊しうる「声の亡霊」でもありうるのだ。
「声紋都市」と「父への手紙」が、最終的にどのような関係におさまるのかは、もはや本番初日を待つほかない。「父への手紙」に関しては、おそらくカフカの同名のテキストが重要なモチーフを提供しているのだろう。カフカは、彼の父親の「声」と、生涯格闘し続けてきた作家である。「父への手紙」の冒頭近くで、カフカは子供のころに父親から受けた恐ろしい体験を、こんな言葉で訴えている。「・・・あなたに何度かどなられました。それでも役立たないとわかると、あなたはわたしをベッドからひっさらって、バルコニーに運び出すと、ピシャリと戸を閉め、しばらく下着のまま、そこに放っておいたのです。(中略)心の傷は残りました。水が飲みたいとグズるような、自分にとって当然のことと、外に運び出されるといった、とてつもなく恐ろしいこととを、自分の性質からして、どうしても結び合わせることができなかったのです。それから数年たっても、思うたびに苦しみました。巨大な男、自分の父親、審判でいうと結審が、ほとんど理由もなくやってきて、夜中に自分をベッドからバルコニーにつれ出しかねない、その人にとってこの自分は、そんなにも取るに足らないものなのだと。」(池内紀訳)。「声」(声紋)は、「法」となり、亡霊のように死ぬまでカフカのひよわな身体を拘束する。ここに描かれているのは、いかにもユダヤ的な父権性、強い父親が支配する権力であり、『カフカ――マイナー文学のために』の著者ドゥルーズ=ガタリは、カフカの文学が、そのような権力空間のなかにその都度引かれていく逃走線として読めることを論証した。それでは、松田正隆は、今回どのような「父」と向かい合おうとしているのだろうか。「マレビトの会」はどのような権力空間に、どのような逃走線を走らせようとしているのか。「私にとっては、私の父がかつて日本軍の兵士であったことは大きな問題であった。そして、そのことは、日本の「父なる者」のことを考えることにもかかわる問題でもある。(中略)父が兵士であったこと。その父が、戦争を生きのびた後、そのことをどのように記憶したのか。その父と、その父にとっての「父なる者=天皇」との関係が敗戦後も、ある意味本質的には何も変わらず維持されたのは何故なのだろう。たとえ、その父を拒絶したとしても、父は姿を変えて私の前に再来するのではないか」(『声紋都市』試演会、08年7月の公演パンフレットより)。
いま、ただひとつ言えることは、『アウトダフェ』と『クリプトグラフ』で、徹底的に「声の匿名性」にこだわった後、この新作で、松田は久し振りに、ある特定の「声」へ向かって接近しようとしていることである。それは、あらゆる匿名の声が生成と消滅を繰り返す場所を、見えないところで支配している権力であり、平戸が彼にとっての故郷だとすれば、そうした権力は、「日本」そのものだと考えられる。「私はこの作品の創作を、故郷にいる父へカメラを向けることから始めた。私は、父のことを誰よりも愛している。だからこそ、父の従軍を許すことはできないし、同時に私自身の父に対する許しを差し出す在り処のことを考えると大きくぶれまくってしまう。しかし、そのことも含めて、この作品に描こうと思ったのだ」(前掲パンフレットより)。私はこの文章を読みながら、彼の90年代前半の代表作に出てくる印象的な登場人物たちのほとんどが、両親不在の、兄弟とその同世代の友人たちが助け合って生活していたことを思い出す。初々しさに満ちたその空間は、いってみれば「母なるもの」に、緩やかに保護されている空間だったといえる。最近黒木和雄によって映画化された『紙屋悦子の青春』で、松田は彼自身の母親をモデルにした。けれども、「父」が直接描かれたことは、おそらくこれまで一度もなかったのである。いつかは越えるべき閾を、いままさに越えようとしているという意味において、『声紋都市――父への手紙』によって私たちは、過去5年にわたる「マレビトの会」の集大成を目撃しつつ、同時に次のステップへと扉を開くスリリングな「第一歩」を目に焼きつけることが可能となるであろう。
森山直人 Naoto Moriyama
1968年生まれ。演劇批評家。京都造形芸術大学芸術学部舞台芸術学科准教授、舞台芸術研究センター主任研究員。『ユリイカ』(青土社)、『PT』(世田谷パブリックシアター)などに論文を多数寄稿する。主な論考に、「過渡期としての舞台空間 小劇場演劇における昭和30年代」(「舞台芸術」連載)他。