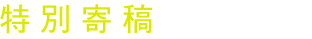「清冽な狂気、またの名を魂の創作衝動」
岩城京子(演劇・舞踊ジャーナリスト)
優れた作家の処女作には「純粋な狂気」ともよべる制御不能な衝動がある。何かを作らねば、何かを表現しなければ、狂ってしまう。いっときの猶予も許さぬ火傷しそうな情動。それが彼/彼女の魂をいやおうなく突き動かす。天児牛大が28歳のときに世に送り出した1978年発表の『金柑少年』にも、こうした創作衝動が間違いなく見てとれる。そしてそれは初演時から四半世紀以上のときを経た今も、色褪せることなく健在。観客は劇場の闇に身を置いたその瞬間から、この清冽な湧水のごとき情動に心をさらわれることになる。
厳密にいえば天児は、この作品に先ずること1年前に実質的な処女作『アマガツ頌』を生みおとしている。だが彼はこの作品の出来映えにあまり納得がいかず、そこで未整理に終わった思考の切片に改めてふるいをかけ、発展的なかたちで本作を創出した。なので山海塾が完全体の創作物として堂々世に送り出した作品としては、この『金柑少年』が初めてのものということになる。初演は東京の日本消防会館ホールにて、たった2日間のみ。ただ「自分のエッセンスが埋めこまれている」と天児自身が言いきる本作は、おのずと口づてに評判を広めてゆき、80年にはついに海外にまで進出。やむにやまれぬ純粋な狂気は、日本を突破し欧州の観客の心にも刺さることになったのだ。
そこでこの稿ではまず、初演当時を振り返り作家の内にはどのような衝動が蠢いていたのか、なぜこのような作品を生み出したいと欲したのか。その原点を明らかにしていこうと思う。『金柑少年』の種火は、どのように燻りはじめたのか。天児本人に問いかけてみた。
「何よりもまず自分のなかにあるとても個人的な疑問符——、これに徹底して集中しくいことで作品は形をなしていきました。具体的にいうなら、まず内的な疑問符としては、私が横須賀で過ごした少年時代にふと思った『なぜ人間の生命にはリミットがあるのか』という恐ろしさ。この原初的な記憶に入り込んでいくかたちで、冒頭からの場面は作りあげられていきました。また外的な疑問符としては『いったいコレオグラフとは何なのか?』という素朴な問いかけ。ただニコニコ笑いながら正面に向かって歩くことや、格闘技のように人間が絡みあうことも、舞踊と言っていいのではないか。つまり踊らない身体で、どれだけ時間と空間に耐えうることができるのか……、という身体の限界にここでは挑戦したかったのです。だからこそ冒頭で、あんなむちゃなことを披露しているんですよ」
夏の夜、宙を仰ぐ少年。彼は盛夏にたちあらわれる不穏な蜃気楼のようにゆらゆら身を揺らしたかと思うと、突如、真後ろにバンッと”跋倒”する。天児が「むちゃなこと」と称するのは、この幕開けの振り付けのこと。ただ人間が真後ろに倒れる。それだけのことをコレオグラフと呼んでもいいのではないか。そんな若き天児青年の直球の疑問が、この振りひとつに集約されている。
ちなみに当時はちょうど、ピナ・バウシュのタンツテアターが世に出始めたころ。世界的な潮流としても「いったい踊る身体とは何なのか」という疑問符が漂いはじめていたころで、完全に個人的な疑問から生じた作品でありながら、天児は期せずしてこの時代の潮流に乗ずることになったのだ。豪奢な孔雀を抱きかかえ鳥の鼓動に呼応してしとやかに歩む青年、二頭身のいびつな豆太郎から雅やかなドレス姿にメタモルフォーズして狂乱的に跳ねる嘆きの聖母、そして水平線の先で逆さ吊りとなり無限の眠りをむさぼる痛ましくも穏やかな生贄。従来のモダンダンスの概念からは想像だにできない異質な身体が、ここでは次々に提示される。
また内的な疑問符に関しては、天児が前述した「生命のリミット」ということだけにとどまらず、様々な熱量の高い感情が舞台から表出されてくる。この世に生まれた歓びと哀しみ、他者とむつみあう温もりと孤独、すっぱだかの身体の猥雑さと静穏さ。なぜかここでは、いっけん相反するとも思える感情がつねに隣り合わせで描かれる。それは少年期と壮年期の迫間で揺れる、若者特有の理屈づけのできぬカオティックな心情をあらわすようでもあるし、また、いまだ何者でもなかった天児青年個人のたゆたう心を象徴しているようにも思える。
「当時、私は小さなアパートのふすまに無数の創作メモを貼りつけていたんです。そして年単位の時間をかけて、そのメモをじっくり眺め、自分のなかで不要だと思える言葉を一枚一枚はがしていった。最終的にそこではがれ落ちることなく残った言葉。それが結果的に、作品の核となり創作につながっていきました。だからこの作品では何よりも、その紙片に端を発する内的な設定を持続させていくことが大切。その場面場面でどのような感情をホールドできるか、そしてその感情が次にどのように転化していくか。正直、そうした内的な変化を追いかけていく緊張感さえ途絶えさせなければ、またまわりの光や音の変化にきちんと対応していけば、おのずと動きはあとから付随してくると思ったのです」
動きはあとから付随してくる――、この言葉に説得力をもたらす、あるエピソードがある。ご存知のように本作では生きた孔雀が、作品中、登場するのだが、初演時は孔雀とリハーサルをする十全な予算がとれず、ほぼぶっつけ本番で当日を迎えることになった。「とにかく孔雀のエネルギーをホールドするぞ」。細かい振りはまったく取り決めず、その設定と大枠の流れだけを持続させることに全精力をかたむけた。そして「まるでチャンスオペレーションのように」細部の動きはあとから舞台上での孔雀とのやりとりで決められていったという。
このように本作は天児個人の非常にインティメットな疑問符から生じた表出物なだけに、振付家はおのずと、4つのソロパートをすべて自身で担い踊ってきた。合計で55分。身体を酷使しつづける独走だ。78年から踊り始め、さすがに15年が経つころには「体力的な限界」を感ずるようになっていた。
「なるべく初演時から15年、原型を変えないことを念頭におき上演しつづけてきたんです。あまり変えることを引き受けてしまうと、作品の質感があるとき違うことになってしまうから。そうならないよう、とにかくさきほど述べた内的な追いかけに集中して、毎回ていねいに踊っていた。けれど40歳を過ぎたあたりで、やはりどうしても体力的に原型を保持するのがムリだということになった。というのもこれは初演時に2日のみ上演するつもりで作った作品なので、体力配分がどうのこうの、ということが全く配慮されていないんです。だから93年に、もうこれ以上踊り続けられないという結論に至り、いちど上演を封印することにした」
しかしこの封印後も、本作の上演を願う声が途絶えることはなかった。
「どうしてもまたキンカンが見たい」
そんな声が世界中で弱まることはなかった。そこで天児は、ひとつの賭けに出る。自分が踊ることが不可能なら、他人の身体に振りを移すことで作品を蘇生させてみよう。そして2005年に彼は本作のリクリエーションに踏み切ったのだ。
繰り返しになるが、本作はあまりに天児個人の原初的な皮膚感覚に負うところが大きい作品なだけに、リクリエーション作業が開始される前は、果たして他の人間が作者の内的な情景を引き受けることができるのか、という危惧も周囲には少なからずあった。だが天児は見事にこの疑念に打ち勝ち、作者個人の肉体から離れながらも、核に宿る凶暴なまでの身体性やカオティックな焦燥感は失わぬ、よりいっそう普遍的な美を保つ作品を完成させた。これにより天児は、本作が、ある特異な個人の身体から離別したところでも生きながらえる強度を持つ真のマスターピースであることを証明。むしろ闇夜に向かいひとり言葉を吐き出してしまうような、青年期特有の危うく純粋な精神と身体さえあれば、本作は半永久的に生き続けることができるのではないか……、という考えをも観客の脳裏に植えつけた。
無論、これは天児本人が踊る『金柑少年』と完全に同じものではない。戦後直後の煤けた横須賀の匂いや、頭上に降る太陽の残酷なぎらつき、水平線を眺め命の終焉について静思した作者個人の皮膚感覚を、そっくりそのまま今の若者たちに移植することはできない。だがより普遍的で根源的な、若者特有の内的変容はきちんとそこに埋めこまれているし、作品のダイナミズムも失われていない。これは、作品が初演から30年もの時を経たことを考えれば驚嘆に値することだ。
28歳の天児青年が純粋な狂気をもって生み出した処女作は、今も、別個の身体を借りて濁りなく清らかに息づいている。
岩城京子 Kyoko Iwaki
1977年、東京都出まれ。86年から91年までニューヨーク在住。94年から96年まで東京バレエ団専科に在籍。慶応義塾大学環境情報学部卒。在学中より舞 台コラム、取材文等を書きはじめる。編集部勤務後、2001年に独立。現在主に演劇・ダンス・トラベルを専門にしたジャーナリスト、エッセイストとして活動。 国内外で取材をこなし年間200本以上の記事を執筆する。主な執筆先に『AERA』『Marie Claire』『NUMERO』など。http://kyokoiwaki.com