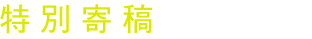上演作品『火の顔』の解説と演出家松井周への期待
新野守広(評論家・立教大学教授)
『火の顔』(1998年初演)は、マリウス・フォン・マイエンブルクの第一作である。2005年6月、ベルリンからシャウビューネが来日した際に、世田谷パブリックシアターで『人形の家』とともに上演された。さらに世田谷パブリックシアターは、マイエンブルクの『エルドラド』(05年6月)と『醜男』(08年6月)をシアタートラムでのリーディング公演に取り上げている。
マイエンブルクは、72年にドイツ南部のミュンヘンに生まれた。ベルリンの壁崩壊後の92年にベルリンに移り、94年から98年にかけてベルリン芸術大学に在籍して創作コースで劇作を学んだ。98年からはベルリンのドイツ座構内の仮設スペース「バラック」の共同制作メンバーとなり、演出家トーマス・オスターマイアーらとともにドイツ演劇の新しい流れの一翼を担った。当時、サラ・ケイン、マーティン・マクドナー、デイヴィッド・ハロワー、マーク・レイヴンヒル、マーティン・クリンプといったイギリスの若い劇作家たちに注目が集まりはじめていた時期だった。「バラック」のチームはこれら未知のイギリスの劇作家やブレヒトを取り上げ、大好評を博し、99年冬にシャウビューネに移った。マイエンブルクは同劇場のドラマトゥルクとなり、以後『パラサイトたち』、『冷たい子供』、『エルドラド』、『醜男』といった新作をコンスタントに発表している。
実は70年代以降のドイツ語圏では、ペーター・ハントケやボート・シュトラウスなどの少数の例外を除いて、新しい劇作家は登場しにくかった。斬新な新解釈を提示する演出家が脚光を浴びたからである。当時の観客を惹きつけたのは、演出家の新演出だった。代表的な演出家は、70年代以降で言えばペーター・シュタインやクラウス・パイマンであり、90年代で言えばフランク・カストルフだった。たいていの劇場のレパートリーはすでにギリシア悲劇から近代劇までの戯曲で埋まっているので、新進の劇作家の戯曲がかかる余地はほとんどない。したがって、イギリスの若い劇作家に注目が集まった90年代後半の気運をとらえてシャウビューネに移ったマイエンブルクの例は、少ないチャンスをとらえてデビューした希な例と言えるだろう。90年代以降のドイツには、マイエンブルクのほかに、デーア・ローアー(64生)、ローラント・シンメルプフェニヒ(67生)、ファルク・リヒター(69生)らの劇作家が登場した。これらの劇作家たちは、崩れた家族関係や曖昧化する人間関係を描く傾向が強い。シンメルプフェニヒもリヒターも、劇作家の育成に力を入れているシャウビューネに足場を得て、劇作家としての活動を拡げることができたと言える。
ではマイエンブルクの『火の顔』は、どのような作品なのだろうか。先行世代との違いはどこにあるのだろう。
『火の顔』は、父母姉弟の四人で構成される家族が崩壊する様を描いている。反抗期を迎えた弟が、姉との近親相姦的な愛を拠り所に両親や学校を切り捨て、ついには両親を殺害し、自分も自殺するという深刻な話だ。子供たちに理解を示す優しい両親は、幼い姉弟からみれば、幸せな家族の書き割り的な存在に過ぎない。一旦子供たちが問題を起こすと、父は母を責めるだけで、観察者の立場から一歩も踏み出すことがない。母はリベラルな教育を勘違いし、息子の前で平気で裸になるほどデリカシーが欠けている。このような両親の描き方に、マイエンブルクの少年時代を形成したリベラルな社会環境への批判を見て取る批評家もいる。超越的な感覚に惹かれる弟は、自分の顔を火で焼くことで、かろうじて存在のバランスを保っている。この家庭に姉の彼氏が入りこみ、事件が起こる。
ミュンヘン生まれのマイエンブルクは、映画監督ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(46年生、82年没)や劇作家フランツ・クサファー・クレッツ(46年生)に代表されるミュンヘン出身の社会派の系列に連なる劇作家であるが、社会の矛盾を観客に問いかけた先行世代の劇作家とはかなり異なる描き方をしている。たとえば路上の若者たちのシーンが印象的なファスビンダーの『出稼ぎ野郎』(69年)は、しらけ切った若者たちの世界にギリシアからの出稼ぎ労働者ヨルゴスが現れることで、外国人に対する偏見や男性社会を肯定するマッチョな男たちを浮かび上がらせる映画である。中産階級出身の夫婦の生活が破綻する様を描く『四季を売る男』(71年)や、初老のドイツ人女性とモロッコからの若い出稼ぎ労働者の不安定な結婚生活を描いた『不安と魂』(73年)も、主人公たちと彼らの周囲の人々の生活には社会的な実体があり、彼らの生活の破綻と危機は70年前後の西ドイツ社会の矛盾を問いかける性質を持っている。
これに対して『火の顔』の暴力は内向的なものであり、社会的な実体は希薄だ。マイエンブルクには、希薄さを拡大して社会の現在形に迫ろうとするところがある。『パラサイトたち』(00年初演)では、人間関係はひどく歪んでいる。リンゴ(男)とベッツィ(女)が二人で住むアパートがある。交通事故で下半身麻痺になったリンゴをベッツィは献身的に介護しているが、リンゴはベッツィに感謝するどころか、むしろ徹底的にいじめ抜く。事故を起こした中年男のムルチャーは介護を引き受ける申し出をし、毎日二人の部屋を訪れるが、それは二人の仲を裂く喜びのためである。ベッツィは、ドメスティック・ヴァイオレンスに苦しむ妹を引き取るが、妹は毒づくばかりで、車椅子生活を余儀なくされているリンゴを徹底的にいじめる。このようにいじめ、いじめられる絶望的な生活を繰り返す果てに、妹は自殺してしまう。
ここに描かれた5人の男女は、誰ひとり社会的責任を担う主体として行動できない。他人に依存し、いじめられる自分をいじめる相手に見せつける歪んだ自己顕示欲が唯一の規範である。ファスビンダーが描いたような中産階級の破綻や、社会の底辺に生きる人々の価値観を肯定する魅力が、マイエンブルクには欠けている。癒しも希望もなく、ただお互いに依存し合って生きている人々を描く彼の世界は、大きな物語が失われた90年代以降の不安定なドイツ社会を浮かび上がらせるのである。
このようなマイエンブルクの世界は、松井周と重なり合うところがある。
そもそもふたりは同じ72年生まれだが、劇作家としての松井周もマイエンブルクも、崩れた家族という共通のテーマを持っている。そして、マイエンブルクがドイツの社会派作家と一線を画すように、松井周は宮本研、福田善之、斎藤憐、永井愛、坂手洋二ら社会の矛盾を取り上げる日本の作家たちとは異なる描き方をする。その特徴は、家族や疑似家族を中心とする人間関係の歪みを通して、あいまいでぼかされたように見えて、しかし非常になまなましい触感で、矛盾の実質を客席に伝えようとしているところにあるだろう。
第一作の『通過』では、寝たきりの母を介護する子供のいない夫婦の生活が描かれる。夫は事故で下半身に怪我をしている。この家に妻の兄とその舎弟たちが入り込むと、家族の輪郭は崩れ、「母-息子」、「義兄-夫-妻-夫の友人」という社会的な人間関係は崩壊してしまう。その結果、欲望に歯止めが失われ、目の前で暴力が繰り広げられる。この事態を戯曲は淡々と描くが、もちろんそこには、心の奥底の叫びを観客に伝えようとする劇作家の切実さが感じられる。ただ劇作家は、希望と絶望が混在する歪んだ風景をそのままに留めておく。なにも解決しないし、展望も開けない。そもそも登場人物たちは解決も展望も望んでいないようにみえる。未来を切り開く意欲が希薄にも思えるこの人々は、しかし一方で非常に大きな情欲や欲望を抱え込んでいて、市民社会や家族という制度からいつの間にかはみ出してしまった自分をもてあましているようだ。このため彼らの何気ない仕草や言葉のささいなニュアンスに、社会の抱える様々な問題が浮かび上がるのである。
このような歪んだ人間関係のなまなましさは、松井周の世界の基本的な特徴をなしている。得体の知れない自然食品の製造工場を運営する疑似家族の危うさを描く『地下室』、去勢手術を受ける男のとまどいがおかしい『ワールドプレミア』、血縁を重視する土着の共同体の奇妙な生活が主題となる『シフト』、施設に預けた母親が誘拐されてとまどう夫婦を描く『カロリーの消費』、40歳を過ぎても引きこもったままの男が登場する『家族の肖像』。これらの戯曲では、現代社会の矛盾が解決不能な形で普段の生活と一体化している。登場人物たちはそこから抜け出るすべも、視点も持っていない。しかも彼らの日常は、けっして平穏無事の静かな世界ではない。他人に暴力を加えたり、暴行を受けて恥辱にまみれたりすることがしばしばある。ちょうど90年代後半のイギリスに登場したサラ・ケインやマーク・レイヴンヒルたちが描いた暴力に曝し/曝される日常が、松井周の世界にはある。それは、明らかに機能不全に陥っているのに、直したり、修正したりする手段がどこにもない世界である。客席で座って見ていると、自分で舞台に上がって、意見や提案をしたい気持ちに駆られる。しかし、もし彼の舞台に上がったとして、いったいどうすればこの世界は変わるのだろう。おそらく舞台上の人間関係の歪みは、客席で見ている観客にしかわからないのだ。登場人物たちは、観客から見てそれがいかに無策に思えようとも、舞台の上の彼らの時間を丹念に生きていくしかない。ここにはマイエンブルクの描く不安定な世界と同質の時代感覚を感じることができる。
マイエンブルクと出会うことで松井周の世界がどのように変わるのか、一観客としてはとても興味がある。ふたりとも高度成長を達成した後の西ドイツと日本で育ち、豊かな消費社会の内実を体験している。多感な時期を迎えた頃に冷戦が終わり、ソ連が崩壊、湾岸戦争が勃発した。松井周演出の『火の顔』はもちろん興味深いが、さらにその後の松井周の活動にとっても、『火の顔』は意義深い舞台となるにちがいない。
新野守広 Morihiro Niino
1958年生まれ。ドイツ演劇研究者。立教大学教授。シアターアーツ編集委員。AICT(国際演劇評論家協会)会員。著書に『演劇都市ベルリン』(れんが書房新社)、共訳書に『ポストドラマ演劇』(同学社)、訳書に『火の顔』(論創社)、『ゴルトベルク変奏曲』(同)、『餌食としての都市』(同)がある。