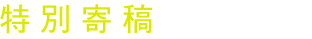曖昧な日本の「わたしたち」
藤原敏史(映画作家)
「わたしたち」という言葉が気持ち悪くなるほど執拗に繰り返される。ドイツ語で書かれ、翻訳不能と言われるほどにドイツ語的な、つまりは主語・主体をはっきりさせなくては文章にならないテクストを、確信犯で強引に日本語にすると、主語がなくとも文章が成立する日本語なら曖昧で済まされる主体が、否応なしに明示されてしまう。
この「わたしたち」の繰り返しは、日本語としてはどう考えても違和感があって不自然に響くはずだ。だが、「自然な日本語」を装うこと自体が、この芝居の主題と性質上、そもそも拒絶されなければならない。
むしろ聞き流されることなく観客の意識の流れにくさびを打ち込むためには、この芝居の日本語は不自然にこそ響かなければならない。そもそも「自然な日本語」とは日本語を母語にする日本人にとって定義しようもなく、無意識の領域に属する感覚に左右されている。だからこそ、言語の機能を意識化するためには、不自然なまでに杓子定規の文法によって、不自然に響かなくてはならないのだ。
「わたしたちは」「わたしたちの」、この一人称複数が国家民族を指し示すとき、その言葉が明瞭に発語されればされるほど、その「わたしたち」の定義がまったく漠然として曖昧なことが逆に際立つ。あたかもその枠組みと定義の空虚さを覆い隠すように、「わたしたち」という存在しない主体が呪文のように繰り返され、刷り込まれて行くかのようにも思える。Port-Bによる日本語版『雲。家。』は、主体が曖昧であるが故に凶暴に暴走した負の歴史を持つ日本的なナショナリズムを、主体つまり主語が構造上は明確なテクストによってあぶり出そうとしている。
分かり易いたとえを用いるならば、日本のナショナリズムをめぐる日本語的に曖昧なテクストを強引に印欧言語に翻訳し、それを再び強引に日本語に訳し直した言葉を聞かされている感覚とでも言うべきだろうか。元々の日本語では「日本人」だったり「大和魂」だったり。「進め一億火の玉だ」だって「一億」が主体なのか、命令形なのかすら定かでない。「欲しがりません勝つまでは」だって「誰が」欲しがらないのかよく分からない。だからこそ「誰が」を考えずにすんなりと広まったのだろうが、「わたしたちは欲しがりません」と言い換えたとたん、「わたしたちは」とは誰なのか、聞いている「わたし」あるいは「僕」が含まれるのかが意識されざるを得ない。それも棒読み調ですらないほど特徴の曖昧な、しかもマッチョ国家主義のステレオタイプからあえてズラした女性の声で「わたしたち」が日本語で繰り返されるとき、「お国のため」なのか「わたしたち日本“人”」のためなのかも定かでなかった日本的ナショナリズムの構造が、逆説的に照射される。
そしてA級戦犯12名の処刑された場にそびえ立つ巨大な直方体、サンシャインである。近代化の象徴というイデオロギーを装って建てられたはずが、その形は巨大な墓標にも見える。A級戦犯といえば靖国神社が話題になるが、戦死者でもないし二名は文民、軍人の多くだって東条首相をはじめ、軍内部の役割でなく政治家として行ったことで処断されたのだから、本来は靖国に属するはずがない。なのになぜか靖国の争乱の元になっている一方で、えらく目立つ高層ビルなのにサンシャインの歴史的な意味を、誰も意識していない。
曖昧と忘却、そこに生まれるズレ−−あそこまで失敗してボロ負けしながら日本的ナショナリズムはほとんど変質することなくなぜ生き延び続けてられたのか、そのメカニズムが作用する無意識こそが、日本語とドイツ語、サンシャインと墓石の直方体という形状的な共通性のあいだの、表象と表象されるもののズレと亀裂から、意識化される。
藤原敏史 (映画作家)
1970年横浜生まれ。東京とパリで育ち、早稲田大学文学部、南カリフォルニア大学映画テレビジョン学部で映画史、映画製作を学ぶ。1994年から映画批評を執筆。2002年、悪友の “イスラエルの山賊” ことアモス・ギタイにそそのかされ、映画『ケドマ』の撮影現場をもののはずみで撮らされたドキュメンタリー『Independence: around the film Kedma a film by Amos Gitai』で監督デビュー。独創的なドキュメンタリー演出を続ける一方で、即興演出を駆使した初の劇映画『ぼくらはもう帰れない』を2006年ベルリン国際映画祭フォーラム部門で上映、世界的な注目を集める。