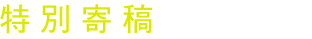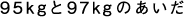- ホーム /
- プログラム /
- 95kgと97kgのあいだ /
- 特別寄稿
『95㎏と97㎏のあいだ』解説
徳永京子(演劇ライター)
役者の上手さとは何を指すのか。職業柄、よくそんなことを考える。
もちろん答えは常時更新中だ。役のキャラクターがにじみ出るたたずまい。自然で、なおかつ観客への浸透度が高いせりふ回し。戯曲や演出への理解度と、それらが力不足である際の応用力。登場した途端、劇場の空気を引き締める集中力──。優れた戯曲とは、いい演出とはどんなものかという問題と同様、その時々で感銘を受けた作品によって、定義は上書きされる。言い換えるなら、定義を上書きしたくなるものこそ私にとっての優れた作品であり、古びていく回答をリフレッシュしてくれる舞台が観たくて、せっせと劇場に通っているのである。
そんな中、更新云々をすっ飛ばし、「役者の上手さとは何を指すのか」という設問そのものの意味をぶち壊してくれたのが、さいたまゴールド・シアターだった。
改めて説明する必要はないかもしれないが、さいたまゴールド・シアターとは、彩の国さいたま芸術劇場が2006年に設立した演劇集団だ。最大の特徴は、入団資格が55歳以上であること。発起人は蜷川幸雄で「年齢を重ねた人々が、その個人史をベースに、身体表現という方法によって新しい自分に出会うことは可能ではないか?」と考えたのが、立ち上げの動機だという。そのため団員は、演劇経験の有無を問わない一般公募で集められた。予想を遥かに上回る1266名の応募者に対し蜷川は、当初予定していた書類選考を「この人達の人生を履歴書1枚で判断できない」と急遽取りやめて全員面接を敢行し、48名の合格者を選出した。
『95kgと97kgのあいだ』は、ゴールド・シアターの2回目の本公演だった(06年に2回の中間発表公演、07年には第1回本公演を行なった)。ストーリーはこうだ。長い行列がある。小競り合いも生まれハラハラするが、次第にそれが、行列の稽古をしている役者の集団だということがわかってくる。と、そこに別の一群が乱入する。乱入したのは、かつて行列を演じた人々。彼らはそこでいきなり稽古を始める。重い砂袋を担いで延々と行進する、という稽古を。この、突如現れる一群を演じたのがゴールド・シアターだった。横田栄司演じる厳しい青年に罵倒され、時にほめられながら、砂袋の重さのわずかな違いの表現に一群は熱中する。目的の見えない、しかし鬼気迫るようなその熱中に感化され、最初に行列の稽古をしていた人々も、やがて砂袋の行進に加わっていく──。
もともとは85年、NINAGAWA STUDIOの若い役者ために書かれた清水邦夫のこの戯曲(ゴールド・シアター公演では、現NINAGAWA STUDIOの団員が最初の行列の役で多数出演)が、何を目的に書かれたかと言えば、それは“虚が実を超える瞬間”だろう。舞台に登場してから幕切れまで、一群がほとんどの時間を費やすのは、腰を落とし、両足を踏ん張り、全身に90数キロの重みを感じるフリをする、という演技だ。せりふらしいせりふはない。もっともらしい起承転結も特にない。誰かの見せ場があるわけではないから、誰も休めない。問われるのは、持続と瞬間。青年はハイスピード、ハイテンションで次々と誰かひとりを指名し、大声でダメ出しをし、自ら汗だくで見本を示しては、また次の役者に指示を出す。応える一群はだから、全身全霊を賭けて重い砂袋を担ぐ瞬間を持続する。その持続と瞬間が役者の心身を追い詰めることは、容易に想像できる。だが追い詰められた彼らの演技はある瞬間、一気に沸点に達し、私達観客へと伝播する。存在するはずのない砂袋を観客に目撃させる。重そうなフリが本当の重さや苦しさや達成感になって、観客に自分の体感と一体化する感覚を体験させる。
第1回の本公演『海上のピクニック』(07年)でゴールド・シアターに教えられたのは、技術的な上手さを凌ぐ味わいだった。短くない時間を非・演劇人として生きてきた人、その体に染みついた様々な癖は、確かに「個人史」と呼べば格好が付くが、実際に観れば、動きも発声もぎこちない。ところが岩松了が書き下ろした戯曲と蜷川の演出は、彼らの頑固なぎこちなさを、豊かな青い苔のごとく扱って、演劇経験の浅さと人生経験の深さが交わるクロスポイントを提示した。その見事なXの文字は、およそ哲学的で残酷な戯曲に、感動的なリアリティをもたらした。
ところが『95kgと97kgのあいだ』でもたらされたのは、感動ではなく体感だった。60代、70代が大半を占めるゴールド・シアターの面々が見えない砂袋を担ぐ。80キロ、90キロ、100キロ。砂袋が見える、砂袋を感じる。さらに95キロと97キロの微妙な差を表現しようとして挫折する。その時はすでに、観客は全身で1キロの差をさぐっているのである。登場人物に感情移入するのとは違う、もっと動物的な感覚。そう、頭を砕かれたのは、平均年齢68歳の役者の肉体が観客とシンクロするほどの動物的なエネルギーを放出していることだった。そこには当然、回路を開いた蜷川の演出があり、それはもちろん演劇メソッドが支えるのだが、目の前にそんなものが放出され、ダイレクトに体に響いてきたら……。「役者の上手さとは何を指すか」などという、所詮、頭で考えたお題は木っぱ微塵となったのだ。以来、「役者の上手さとは何を指すか」と考える時、「ただし、さいたまゴールド・シアターを除いて」と考えるようになり、今日に至るまで残念ながら、ゴールド・シアターを含めた定義を更新するには至っていないのである。
徳永京子 Kyoko Tokunaga / 演劇ライター
OL、コピーライターを経て、フリーランスの演劇ライターに。演劇専門誌、情報誌、公演パンフレットを中心に、インタビュー、作品解説、劇評等を執筆。現在、「シアターガイド」(モーニングデスク)にて『プロデューサーの視線』、「花椿」(資生堂)にて『ステージが』、『Choice!』(ネビュラエクストラサポート)にて『Stage Choice!』を連載中。東京芸術劇場運営委員および事業企画委員。