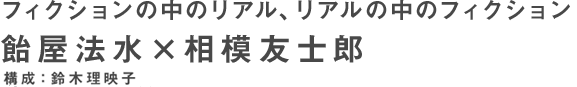F/T09春の『転校生』では平田オリザの会話劇に今を生きる女子高生の「生の時間」を重ね、続く秋の『4.48サイコシス』ではサラ・ケインの病的ともいえる断片的テキストをさまざまな属性(男・女・国籍など)を持った身体と声で舞台に立体化した飴屋法水。一方、27歳の演出家・相模友士郎は、70歳以上の高齢者たちと共に彼らの個人史を再構成、現代を生きる身体との対比の中に「わたしたち」の生と死を描く『DRAMATHOLOGY/ドラマソロジー』で、今年F/Tに初登場する。二人はこの日が初対面。だが、リアルとフィクションの関係について、俳優ではない人々との共同作業について......その対話は当初から核心をつくものとなった。
――お二人は共に「生」や「存在」をテーマにした創作活動をされていますね。相模さんは飴屋さんの作品はVTRでごらんになったそうですが、作風や手法も含め、ご自身との共通点や気になったポイントはありましたか。
相模 『転校生』を観ていて、まず気になったのは衣裳のことでした。同じ高校の生徒を演じる子たちがそれぞれ違った制服を着ていて。あれはたぶん本人が通っている学校の制服ですよね。『転校生』という戯曲がそこにはあって、女子高生を演じている人がいる。でもその人たちは普段の生活でも着ているであろう服を着ている。そのねじれは演劇でフィクションをつくるうえでの「止め具」のように見えたんですが、実際はどんな意図があったんでしょうか。例えば僕の『DRAMATHOLOGY/ドラマソロジー』でも、出演者のお年寄りたちは「舞台に出るならみんなでおそろいの衣裳を着よう」とかっていったんです。僕も「そこは普通で」って止めたんですけど......飴屋さんも全部そろえようとは思われなかったんですよね。

飴屋 確かにそれには違和感がありましたね。そろえてしまえば台本どおりの「ひとつのクラス」ができあがるわけだから、普通に考えればそろっていた方がいいのかもしれない。でもあの時は、そうするとわざわざ本物の女子高生に『転校生』をやってもらう必要がなくなっちゃうって気がしたんです。僕はオーディションでも自分からは誰も落としていませんから。相模さんの作品のおじいさん・おばあさんと同じだと思うけど、結局、女子高生に向いてない女子高生なんていないんですよね。ただ「どうしてオーディション受けたの?」って聞くと、彼女たちは「舞台に立ってみたかった」とか「違う自分になれるのが面白い」って答える。で、僕はその時に「違う自分にはなれないよ」って話をしたんです。やっぱり演劇ってフィクションなんだけど、人間がそれを演じるからには完全な虚構にはならない。つまり演劇の現場は「演技」とはなにかってことを一回ごとに考え、つくっているんだと思うんです。だから「なろうとする」のも演劇の大きな方向の一つなんだけど、それと同じだけ「なれない」というのも大きな方向で。そのバランスを細かく考えていくのが、フィクションをつくる時に僕がしょっちゅうやっていることなんですよね。既存のテキストをやるときに、いわゆる役者さんは使わないことになっちゃうのもそういうことで。それで『転校生』の時には、同じ衣裳を着ることが致命的な問題になると感じたんだと思う。
飴屋法水 ● あめや・のりみず
1961年生まれ。唐十郎主宰の状況劇場を経て、東京グランギニョル、M.M.M.を結成し機械と肉体の融合を図る特異な演劇活動を展開。90年代は活動領域を美術へと移行するも、95年のベネチア・ビエンナーレ参加後、作家活動を停止。同年「動物堂」を開店し、動物の飼育・販売を始める。2005年、24日間箱の中に自身が入り続ける「バ ング ント」展で美術活動を、07年に『転校生』の演出(F/T09春で再演)で演劇活動を再開。
相模友士郎 ● さがみ・ゆうじろう
1982年福井県生まれ。京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科卒。00年より映画製作を手がけ、国内外で作品を発表。04年より舞台作品の創作を始める。映画「穴る」、演劇作品『SM』が共に同大学卒業制作で最優秀賞に選出。映画と舞台を横断して活動し、双方向的な視点から身体や劇を捉え直している。また、さまざまな舞台公演で宣伝美術を手掛け、「プロセス太田省吾演劇論集」などの本の装丁も行っている。