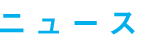 Tweet |

- e.g.MILK
- 空 (UTSUBO)
- 小川水素Co.
- 壁ノ花団
- かもめマシーン
- 国枝昌人×古舘奈津子
- KUNIO
- けのび
- The end of company ジエン社
- 栩秋太洋
- 鳥公園
- 捩子ぴじん
- バナナ学園純情乙女組
- ピーチャム・カンパニー
- FUKAIPRODUCE羽衣
- 村川拓也
- 夕暮れ社 弱男ユニット
- ロロ

e.g.MILK (代表:石川勇太)
私の作品は“時間”という事を主にテーマとして捉えています。常に変わらないものは時間であり、どの人にも平等、均等に与えられているもの。しかし、それは国、想い、感情、空間、記憶によって、常にねじ曲げられ、変化し、どうしても作用されてしまう。それは私にとって、目まぐるしく動く現代の東京、日本を顕著に現すので、非常に強いイメージ、インスピレーションを与えてくれます。私の作品の中ではスピードの言語化、スローテンポ、時間軸の身体化、物の擬人化を主に扱っています。そしてそこに人の感情と記憶、何かのメタファー(オブジェクト)をその間にコラージュし織り交ぜて行く事で現在、未来、過去をつなぐ一つの強い志向性を生み出してくれる。人類は何を見たいのか、どこに行くのか、そこには、混沌と迷い、決断があり、何に納得し記憶を呼び戻すのか、そこには常に前を刻む、時間という事を意識的に常に入れる事で個々人の感覚、思いを刺激し面白いだけでない、何かを感じられる作品を生み出すと信じています。

空 (UTSUBO) (代表:岸本佳子)
日本語を話す英語話者と、英語ができる日本人と、日本語を母国語としない日本人と、日本語を母国語とする外国人と、英語以外の言語を第二言語とする日本人と、英語以外の言語を母国語とする日本語話者の外国人とが会話を交わす場面。そのような時、自分が他者の言語の中に入って行く場合もあれば、母語の異なる他者がこちらの言語に入って来る場合もあります。前者の場合、自分が他者の言語にどれだけ精通しているかによって話す内容が限られてきます。何を話したいか、よりも、何が話せるか、のほうに会話の内容が寄り添っていくわけです。後者の場合、相手への気遣いが先走って日本語のほうが変に英単語まじりになったり、話したかったことと話している内容が微妙にずれていったりすることがあります。いずれの体験も、母語の中だけでは体験できない楽しさや、難しさや、絶望や、悲しみや、その他もろもろの感情や激情を喚起してくれます。そして同時に、さまざまな問いも生まれます。そもそも、母語、とは何なのか。言語が違うとなぜ身振りもこんなに違うのか。なぜ、こんなに常識のラインが噛み合ないのか。言葉の問題は、果たして言葉の問題なのか。空(UTSUBO)は、ポーランド、韓国、アメリカ、ガンビア、イラン、フランス、中国、イギリスといった多国籍メンバーで、日本語と英語を共通言語として使いながら、共有する母語のない他者同士の共存への方法を模索していきます。

小川水素Co. (代表:小川水素)
私は「ダンス」とはどうすればできるのかということをつねづね考えてきましたが、4年ほど前から、身体のポーズや動きの型を決めるのではなく、‘ルール’を設定するという方法を実践しています。この方法であれば、どのような人でも平等に参加することができるし、また参加者同士の合意によって‘ルール’を変化させたり、新たに設定したり、と参加者に知的かつ主体的に‘ダンス’に関わることを可能にするからです。 ‘ルール’を媒介にして表現される‘ダンス’は、参加者に‘動き’を通した関わり合い、すなわち動きにおける‘コミュニケーション’を生みだします。それは、‘ダンス’を、社会に対して開かれたものへと変える力を持っています。また一方で、‘ルール’を媒介にしたダンスは、互いの’コミュニケーション’なしでは成り立たないと言うこともできます。国籍や性別など背景の異なる人々が、同じ‘動きのルール’を行うとき、彼らはそれまでに身につけた各々個人の価値観について、身体感覚を通して改めて気づくことになるでしょう。人間の動きに‘ルール’を与え、それを‘ダンス’と定義してゆくことは、身体の元々持っている多様な在り方を再認識することにもつながります。私は、様々な人たちとコミュニケーションをとりながら、‘動きにおけるルール’を作ってゆくとともに、統一された価値観に向かいがちな社会へ、身体の多義性を訴えて行きたいと考えています。

壁ノ花団 (代表:水沼健)
物語の新しい形式を模索することを主題にしています。どのような形式であれ、物語を表すとき、ひとつの形式を選択せざるを得ないという問題は好むと好まざるとにかかわらず現代舞台芸術における表現上の共通した問題で、私たちはその問題を意識的に前面化して扱うことでカンパニーの特徴を獲得したいと考えています。これまでは時間や空間を重層的に扱ったり、時間を逆転して展開させたり、また俳優に複数の人格を与え、その乗り換えをさせたりして私たちなりの表現意識を形にしようとしてきました。非日常的な設定にこだわり、身近なリアリティから距離を置くこと、また簡素な舞台にすることで演劇の根源的な強みと考える俳優の身体の印象、存在と言葉のかかわりあいの不思議さを最大化しようとすることも私たちの特徴だと考えます。これまで模索してきた劇作上で古典(折口信夫、ドストエフスキー等)を題材に取り上げることによって先人からの文学的遺産を引き継ぎ、私たちなりに捉え直し普遍性と現代性を見出す作業に関しても、引き続き継続的に行いたいと考えています。

かもめマシーン (代表:萩原雄太)
演劇やダンスなどのパフォーミングアーツにおける身体性とは、日常の身体性の延長にあるような存在でなければならないのではないかと考えている。それは「ナチュラル」であることを意味するのではなく、あくまで「リアル」であることを求めるのではないだろうか。そして、そのためには「身体」の位相はもちろん、その身体が立脚するもの(劇場、今、ここ、観客、演技、歴史etc)の捉え直しが必要になるのではないか。それによって、意識が介在しないほどに微細な「動かされる身体」とでも呼べるようなものが見えてくるのではないかと考えている。舞台芸術や現代社会、我々が無自覚に前提として考えているあらゆるものを疑うことによって、あるいはそのような身体を見いだすことは可能なのではないか。つまり、我々が何によって縛られているのか、何によって「動かされているのか」をもう一度見つめ直したい。そして、そんな身体を見つめる作業を積み重ねることによって、人間の/現代の/トーキョーの身体に対する可能性を模索しつつ検証する。

国枝昌人×古舘奈津子 (代表:古舘奈津子)
近年のコンテンポラリーダンス作品において、安直なおもしろさや表面上のインパクトが多く、身体への探求をあまり感じない所があります。私達はテーマとして物語性や起承転結の排除、身体がそこにある状態で外部や内部の刺激によりいかに身体が変化していくかに興味を持ち、その変化を受け新しいムーブメントへの挑戦を試みます。既に出来上がったフォルムやフレーズではなく、それらが完成される前に次へ移行する事でムーブメントが作れないかを最近のテーマとしています。また、デュオでありながらそうではない可能性の模索もテーマの1つです。このようなテーマを持つ上で問題として意識せざるをえないのは、自身の作品性からも一般的な観客に受け入れられにくいと感じる事です。特にコンテンポラリーダンスは市場もあまりなく演劇に比べ公演回数も少なく、しかも観客層が限られている現状があり、一般的な観客が様々な作品を体感する機会が格段に少ないからだと思われます。観客が安直なおもしろさだけにとらわれず、観客自身が「体感する」事によって作品に参加し考えていけるような作品作りが必要と考えます。また、そのような機会を増やす為にもアーティスト自身がより地元地域との関わりが必要であり、またマーケットとして機能してゆく為には底辺にいる我々が今なにをすべきかを考える必要があると考えます。

KUNIO (代表:杉原邦生)
僕にとって、昨今の小劇場界の描く〈世界〉は小さすぎるのではないかと感じています。インターネットの普及や価値観の多様化によって個人の〈世界〉が狭く小さなものになってしまっていることは言うまでもないことですが、それは僕たちが実際に生きている〈世界〉とは距離のあるもの、どこか切り離されてしまったものになっていないでしょうか?もちろん、身近なところからテーマを導き出し、作品をつくるということはとても真っ当なことだと思いますし、素直で正直な姿勢であると感じます。しかし、それだけで良いのでしょうか?その作品によって描かれている劇世界は、個人の〈世界〉を抜け出せているでしょうか?もっと広い意味での〈世界〉へと繋がっているでしょうか?その問いが僕を名作/傑作と言われる戯曲に向かわせているのではないかと感じています。その戯曲に、演出家として真っ正面からぶつかっていくこと。そのことが、いま、僕にとってもっとも重要なことだと感じています。

けのび (代表:羽鳥嘉郎)
生活局面をも含む劇というアイデアを中心に、「いかにしてともに生きるか」をテーマとして活動している。「ともに生きる」とはもしかしたら「折衝の可能性を保持する」ことなのかもしれないと考えはじめており、物事・出来事の始まりや終わりではなく、続けるための活動を半ば専門とする。2009・2010年度は、「ひとの可能性を殺さない」などといった心がけ(ディレクション)を文字通りに行い続けることをはじめとし、そうしたいつでも使える心がけを、逆にパフォーマンスワークを繰り返す事によって引き出す、といったスタイルで活動。2011年1月現在は、どうして、「ともに生きる」ための努力が常に個人的なものであり、それぞれが「心がけ」たりしなくてはいけないのか?という疑問を胸に、信仰や宗教や「よさ」が私的・個人的なものとして扱われている現状に、はたらきかけようとしている。そこには明らかに権力構造があり、問題として顕在化しうると考えているため。具体的には、信仰(の対象)を追求し続ける仕組みを制作してしまうことを目論む。現在の思考モデルの一つには、札幌のNPO「葬送を考える市民の会」の事例がある。

The end of company ジエン社 (代表:作者本介)
絶対正しい事なのかもしれない事の一つに「やる気がある事」というものがあります。例えば、なんでアルバイトの志望動機や自己PRに、やる気を出さなければいけないのか。やる気がないなら、自殺しろ。タウンワークはそう言っているのではないか、と私はつい疑っています。やる気がある――もっといえば「劇的」な感じにあふれている。それは、どうなんだ。大田省吾は著書『劇の希望』の中でこういいます。「私たちは<劇>を失ったのではなく、むしろ<劇>を強いられている。」と。この「強いられている」現在に、むかつきを感じるのです。我々には、もっといろいろある、というか、そんなにいろいろないのだ、と。その、いろいろある、何もない何かを、我々はしたいし、してきました。奴らが、あなた方が、私たちが、省略してきたり「見てるつもりで見ない」ものを、ジエン社は、やります。絶対に正しいとされている「やる気」を否定するために、死ぬ気で「死ぬ気」を否定するために、やたらやる気を強制する「現在」に歯向かうために、私たちは、やる気なく舞台に立ちます。なぜか。ただ単に、自殺しないために。自殺させられないために。やる気のない自分自身に自殺を強要させられないために。やる気がなくても生きるために。単に、生きるために。やる気がない人が、やる気なくいます。物語はありますが、強くはありません。私たちはそういう事をやっています。

栩秋太洋
「存在」つまり「ある」ということの確かさ、それそのものが美しいと思います。「存在」をテーマに振付作品として今取組んでいるのは、言語化されない原初的表現に立ち戻ることです。なぜなら、そこにこそ言葉や構造が生まれる瞬間があり、それは体と不可分だからこそ身体感覚としての共感と強いリアリティを持つことができるからです。私にとってダンスとは表現とは、何か体の明確な動きや形を通して名付け難い内的感覚に至ること、また一方では、明確な内的感覚から名付け難い動きに至ることです。したがって所謂ダンスというような元気なエネルギーを発散させることではなく、ただ人が立ち尽くしているように見える空間にも何一つ欠けることのない宇宙を見出そうとしています。その手がかりを求めようとしたときに、私は舞踏をやっていることにあらためて気付きました。奇抜なアイデアを考え出すことはできないので、先人の問題意識を自分に引き受けたところに新しい表現の可能性を見出したい。

鳥公園 (代表:西尾佳織)
鳥公園は、家族、生理現象、時間の経過、死といった、人がどうしようもなく行き当たる事象を題材に、社会の「正しさ」の枠組みから外されてしまっているもの、けれど確かに存在するものたちをすくい上げ、柔らかな光をあてようと試みている。《「正しさ」からこぼれて、そうしかいられない私(たち)のみっともなさは、肯定も解決もできないけれど、一人では持ちきれないこのどうしようもなさを、二人で、三人で、大勢で、ただ持っておく。見ないフリをしないで、存在するものをただ見る。それはきっと変化していく。よい方向へ進むのだろうと、悪い方向へ進むのだろうと、変わり得ることは希望です。(西尾佳織/鳥公園主宰)》事物の質感、手触りを原形質のまま手渡すような戯曲の言葉づかいが特徴。また空間における美術・光・音・身体の配置にこだわることで、それらのより内に奥に存在しているはずのヴィセラル〈内臓的〉な運動に触れ、顕わにするような演出を心がけている。また最近は、今いる場所(例えば東京)以外の土地のリアリティに関心をもち、様々な場所で生きる人たちに出会いたいとも願っている。なにはともあれ、お茶目さとユーモアは忘れない。

捩子ぴじん
コンビニエンスストアでのアルバイトを題材に作品をつくったり、また実際にコンビニエンスストアに観客を呼び、アルバイトの仕事を見せるなど、身近な生活をダンスとして取り出し作品にしたり、ダンスが日常に内包されている可能性を見るための活動をしている。劇団を退団し、振付家として活動を始めた当初、日本では“コンテンポラリーダンス”という、それまでダンスと呼ばれなかったものをダンスと呼ぶ、ダンスとして見ることが出来るということを示そうとする特殊なムーブメントが最盛期だった。それらは“コンテンポラリーダンス”という名前を与えられたことにより、ムーブメントとしての役割を終え、今ではそのムーブメントを支えていた作家が自分のダンス作品と、与えられた名前との間に違和感を感じながら作品をつくっており、その名前で呼ばれることを嫌悪するものもいる。しかし、コンテンポラリーダンスは終わっても、今までにないやり方を見つけることと、それをダンスと呼ぶことは可能である、ということを示したい。日本で生まれた舞踏が、世界に広まるほどの力を持ったダンス・ムーブメントになったように、これから生まれる作家が新しい力を持ったムーブメントを生み出すことが出来るように、ダンスにありとあらゆる可能性を残したい。

バナナ学園純情乙女組 (代表:二階堂瞳子)
★ 実はバナナ学園って真性のヲタではない
★ 覚めた目線で悪意を持ってヲタネタを扱っている
★ 客席のヲタこそがアイドルよりも文化
★ 各人のコンプレックスの昇華
★ 恥ずかしい過去の肯定
★ 普通の演劇には興味ありません!!!!!!!!!!!!!
★ 普通の演劇ツーエイトで飽きるし
★ もてあます肉体
★ 生き急ぐ肉体
★ 騒音
現状にアゲインスト
★ なんだかんだいってみんなヲタ的な事通ってるだろうし、そーゆー隠したがる恥部こそ日本のひとつの真実だろと 何みんなカッコつけてんのかと 肉体肉体もてあます肉体肉体肉体肉体騒音肉体獣肉体芸術生き急ぐ肉体
★ バナナ制服着て、誰もが演じてるようだけどその人の黒歴史をきちんと武器にしてる
★ でも破壊で終わってないから、きちんと昇華発散して気持ちよく終わるから同じようなコンプレックスを持つひとが見れば、救われるような気持ちになるんじゃないかな
★ やってることは原始的
ただ、時代性とリンクしてるから今この表現をやる必然性がある

ピーチャム・カンパニー (代表:川口典成)
ピーチャム・カンパニーの目指す演劇のかたちは、「シビアな現実認識と胸躍るロマンの同居する新しい現代のドラマを介した、役者と観客との間での濃密な「出来事」の共有としての演劇」である。作り手の生き様や眼差しが観客のそれと共感や反発を通じて交錯してゆくことで、クリエイターと観客とがともに新たな関係のしかたの地平を発見してゆくような<場>として、演劇の上演を位置づけ、実践を続けている。その上で、かつてありし世界への鎮魂とやがて来る世界への予祝という意味での祝祭となるような劇空間を創造し、演劇の本源的可能性を最大限に追求した作品作りを目指している。また現在は、われわれの暮らす東京という都市への眼差しを問い直す<urban theatre series>を継続しており、演劇が上演される地理的空間との新たな関係のしかたを発見してゆくことを目論んでいる。創作にあたり、脚本としては、いかにして現代演劇に古典的なまでの強度を持たせるか、という問題に対して、戯曲の言葉によって回答することを大目標とし、主題の普遍性と、ポエジーを宿す凝縮された文体とを、徹底して追求している。演出としては、他者の痕跡としての言葉と俳優の生身の身体とが緊張関係を内包しながら摩擦を続けることで生まれてくるエネルギーの意識的/無意識的な噴出を第一原理として、創作を行っている。

FUKAIPRODUCE羽衣 (代表:深井順子)
現代に生きる人々が、中々露わにし辛い人間の根幹のコク深さを、人(俳優)と人(観客)との生(ナマ)のやりとりである演劇だからこそ屈託なく表現することにより、「演劇ブルース」を奏でたいと思っています。私たちは自分達の演劇スタイルを「妙ージカル」と称して、歌と踊りの妙な世界、妙という言葉の持つ、一風変わっているという意味と、なんともいえないほど美しいという意味の両方が、そこはかとなく漂う世界を目指し作品を創っています。俳優の発する全ての言葉は音であり、言葉の持つ意味は音によって千変万化し、時に、音によって言葉は意味を超えます。決して国語辞典では検索できない、その情感こそが、人間の根幹のコク深さのようなものであり、それこそが言葉の持つ力であると考えています。言葉が、俳優を通して意味を超える音へと昇華されることによって生まれる人間賛歌を、劇場に響かせたいと思っています。素朴な人間の力は虚構の中にしか存在できないかもしれない現代に、その虚構を、生々しく観客に届けるため、傍観することができない程、圧倒的な「生」のエネルギーを持つ作品であることで、演劇でしか味わえない密度の濃い空間、表現の豊かさを観客と共有することを目指しています。

村川拓也
「労働」というものに関心があります。とりあえず演劇表現と「労働」についての事を書きます。関心を持った原因は、演劇は仕事になるのか、ということで、現在の私生活の状況から発したと思います。僕は演劇に関わって、一度もはっきりと仕事をしているという感覚になったことがなく、それよりは生活の為のアルバイトやその他の仕事に就いている時の方が仕事をしている、働いている、という感覚を得る事ができます。ギャラがあるかないか関係なくです。自分にとってはだからどうだという事はないのですが、特に演劇に出演する俳優にその事を考えてしまいます。つまり、俳優は仕事か、という事です。僕の作品では俳優として活動をしていない人間が出演する事が多く、そんな人たちにどうやって舞台に立ってもらうか、どういうつもりで舞台に立つのかという事が常に問題になります。なんの為に? それは俳優それぞれ思いがあるのかもしれません。欲望かもしれないし、息抜きかもしれないし、単に頼まれたからかもしれません。僕は俳優を「労働」するものとして舞台に上げたいと思います。俳優個人の思いとは離れた状態で、単に「労働」する、そんな人間の姿が見たいと思い始めています。これは演劇を仕事として獲得したいというような思いがあるからではなく、演劇表現をどうやって自分なりにとらえるか、という思いがあるからです。

夕暮れ社 弱男ユニット (代表:村上慎太郎)
最近、演劇を観にいっても〈それら〉とうまく向き合えない。それは、何故か?演劇を始めたころ、我々は、〈劇場〉で公演をすることが様々な理由で、実現できませんでした。なので結成してから3年くらいは、砂浜や、劇場ロビー、ライブハウス、会議中の事務室前などで、「演劇」を上演してきました。やがて、ここ2年くらいで、劇場での上演または公演が可能になってきて、今度は逆に「劇場で演劇をやる」ことに違和感を覚えるようになってきました。それまで、照明も音響も一切ない環境でやってきたので、劇場に漂う特殊性みたいなものが気になって仕方ないのです。例えば、そこにある歴史や社会であったり、はたまた施工主の顔でさえ気になりはじめました。だから、〈それら〉とうまく向き合おうと、『演劇の言語・演劇の形式』の〈再構築〉を考えるようになりました。新しいものを作ろうと上へ上へと創作の枝葉を伸ばすのではなく、「横移動」を繰り返し新たな〈鉱脈〉を探そうとしているのかもしれません。観劇時にうまく向き合えないと思っていた部分を作品にするにしたがって、濁っていた劇場に漂う特殊性が純化されてくるように、〈それら〉をひとつひとつ突き詰めようとしています。『演劇の言語・演劇の形式』が世界レベルで対話されるとき、より根もとに近い部分〈出発点〉にあるのが我々が創作すべき場所なのかもしれないと考えています。

ロロ (代表:三浦直之)
誰かと誰かが恋に落ちて、もちろんその瞬間に二人はそれを運命だとおもって、こんな恋はもう二度とないとおもって、でももちろんそんなことはなくて何回も繰り返されてきた恋のうちの一つにすぎなくて、それでもまた誰かと誰かは恋に落ちて、もちろんその瞬間に二人はそれを運命だとおもって・・・。でも、その瞬間に誰かが誰かを好きになったていうことは、それがまた何回も繰り返されたって、他の誰かではなくてその人を選んだっていうことは、絶対にポジティブで、だから、ロロは恋の話ばっかりです。いまここでおこることが明日もそこでおこるということ、昨日もおこったということ、明日はもうおこらないかもしれないということ、もしかしたらそれはおこらなかったかもしれないということ、しかし、いまここでそれはおこっているということ。観客が一回の上演をみながらその外側に想いを馳せていくような、たくさんの別の可能性に想いを馳せていくような演劇を目指します。



